世界のエネルギー問題を見る目
日本での気候変動対策を考えるにあたって、大きな影響力を持つ米国の動向を正しく捉えることは必須だ。それも表面的なことではなく、深層まで理解する必要がある。2008年の米国の政権交代後、追随する日本は気候変動問題から取り残されることになった。現在の米国を見誤ると、日本は同じことを繰り返しかねない。大統領選を控えた米国の気候変動政策は、これからどこに向かおうとしているのか。afterFITの前田雄大氏が解説する。
新型コロナウイルスと人種差別問題で混迷する米国
米国が揺れている。
新型コロナウイルス被害の拡大とそれへの政府の対応、それに端を発した経済不況、失業の急増加、そして直近では、大きなムーブメントを米国内で引き起こしている人種主義問題、そしてボルトン前大統領補佐官による政権内幕の暴露。
一見、気候変動とは無関係に見えるこの揺らぎ。筆者は、ここにこそ、世界的な気候変動、そして再生可能エネルギーの今後を占う重要な論点が隠されていると考えている。米国の動向は、やはり国際的な気候変動や再生可能エネルギーに与える影響が非常に大きいからだ。
この米国の揺らぎの影響いかんでは米国、そして世界の気候変動事情は一変する。今回はそうした米国の各種動向を読み解いていきたい。

大統領選翌日がパリ協定脱退完了という巡りあわせ
周知のとおり、そもそも2020年は、気候変動にとって大きな節目の年であると目されてきた。それには大きくふたつの意味があると考える。
ひとつには、パリ協定の本格運用が開始する年という意味において。これは採択時から設定されていたものだ。
そしてもうひとつ、パリ協定が採択されたとき、政治的に主導する役割を担っていたアメリカが、その協定から脱退するか否かが2020年11月に決定する、という意味においてである。パリ協定にとって2020年という年は不思議な縁がある年なのだ。
パリ協定はその規定上、締約国になってから3年間は脱退手続きを取れない。そして、脱退手続きが効力を発揮するのには、さらに1年かかる規定となっている。
パリ協定は、2016年11月4日に発効されたため、同日よりも前にパリ協定を批准していた米国を含む全ての国は、この2016年11月4日をもってパリ協定の締約国となった。したがって、米国がパリ協定からの脱退手続きを取れるのは、協定の規定上、締約国となった日から3年が経過した2019年11月4日が最速である。その日に手続きをとったとして、それが効力を発揮し、脱退完了は2020年11月4日である。
事実、米国はこの最速のスケジュールで手続きを進めており、2019年11月4日に国務省は国連に対して脱退手続きを申請している。
つくづくトランプ大統領とパリ協定は縁があると筆者が思うのは、どういう運命のいたずらか、大統領選挙の日が2020年11月3日であり、パリ協定脱退手続きが効力を発揮する日の前日であるからである。
とても偶然とは思えない日程であるが、11月3日の選挙の帰結として起きるであろうことを単純に考えれば、トランプ大統領が再選すれば、パリ協定から米国は脱退することになる。
では、バイデン候補が当選した場合はどうなるか。
同じく11月4日に、形式的には脱退手続きが完了してしまうものの、バイデン候補は大統領就任後にパリ協定の再締結を行うであろうから、2021年1月20日の就任までだけの形骸化した脱退期間となるだろう。国際的な受け止めとしては実質、米国のパリ協定への回帰が11月3日に決定することになる。
さらに理論的に日付だけ見れば、米国のパリ協定脱退がギリギリで回避されることも可能な日程でもある。
これがなぜ、そしてどのように世界の気候変動、再生可能エネルギーの今後を左右するのだろうか。
それを見抜くカギは、トランプが米国大統領であったこの3年半余りに起こった、世界的な気候変動への動きを振り返ると浮かび上がってくる。そのひとつが「ねじれの構図の発生」だ。

トランプ政権が、気候変動対策を活性化? 脱炭素化は進むのか
トランプ大統領は2016年の大統領選挙の以前から一貫して、パリ協定下の気候変動対策の推進に真っ向から反対の立場をとってきた。2017年6月に大統領がパリ協定脱退を表明した際のステートメントにおける同大統領の主張は、おおむね次のとおりだ。
「パリ協定下においては、例えば中国やインドは排出増を許されている。一方で、米国は自国民の負担に依って排出を減らすこととなっている。こんな不公平なことはない。だから米国はパリ協定から脱退する」。
この大統領の発言を受け、アメリカは真っぷたつに分かれ、大きな議論を呼んだ。
大統領が自らの支持層に対して石炭関連の従事者の雇用も含めて守るとして、それが熱狂を呼ぶ反面、気候変動対策推進派は、(政府まかせではなく)自らがアクションを取らなくてはならないとの危機感を募らせた。非国家主体(アクター)は、気候変動対策を推進していくイニシアティブをいくつも立ち上げていった。
We Are Still In(我々は(パリ協定に)残る)キャンペーンからはじまるイニシアティブの発足や、カリフォルニア州が主催したGlobal Climate Action Summitイベント(2018年)の開催などはその代表格だ。
トランプ政権にとっては皮肉な話ではあるが、国の政策に反発する形で、州によっては逆に気候変動対策が進む(連邦制ならではの動きである)など、対策の推進力創出につながった側面も観察された。
しかも、(気候変動対策に熱心であった)オバマ政権下では見られなかったほどのドライブ力をもって。
民間においてはテスラが好業績を継続し、AppleやGoogleといった企業が再生可能エネルギーでの自社電力100%調達を達成する等、象徴的な進展も見られ、実際に再生可能エネルギーの導入も、先述した州政府独自の政策に呼応する形で堅調に進んでいる。
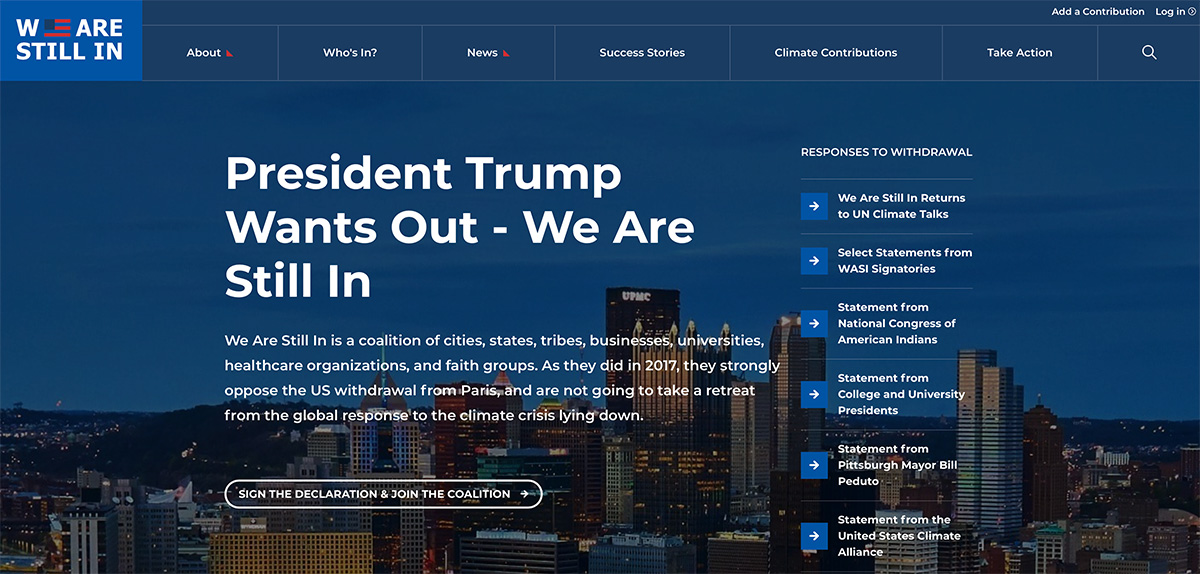
トランプ政権下で起きた「ねじれ」の発生
一方、筆者が行政にいる中で痛感したことであるが、民間セクターは行政が発表する政策のメッセージ効果、予見性というのを非常に大事にする。政府の方針が気候変動対策について抑制的である中、投資行動を本来に比べ控える、ないし、タイミングを遅らせるなどの行動を、目立たないながらとる企業が米国に多く存在しても、それは不思議ではない。
先述のとおり、米国の中ではトランプ政権の政策に反発する形で素地が整った。また、そもそも再生可能エネルギーの拡大は国際的に不可逆な現象であり、その波及的影響で米国でも再生可能エネルギーの導入が進んだとも取れる。
しかし、AppleやGoogleのような象徴的な動きはあくまでも、予見性を無視しても自社の戦略を貫くことができる一部企業によるやはり“象徴的”な現象であって、エネルギーシフトが米国全体の動きにまで浸透しているのか、その部分の考察は高度な精査が必要である。
事実、2018年の米国の温室効果ガス排出量は前年比で3.1%増であったのはmassでのエネルギーシフトは生じていない証左の一つと考えられる。
それでも、国際的にはビジネスにおいても脱炭素の流れは決定的だ。トランプ大統領の政策が反気候変動で一貫すればするほど、国際的な潮流に敏感な民間セクターにおいては、本来なら投下するはずであった気候変動対策に対するエネルギーが、蓋をされたように沸々と溜まっており、現在は噴出圧力が高まっている状況であると筆者は分析している。
つまり、本来であれば、さほど進まなかったであろう気候変動のイニシアティブが大きなドライブ力をもって進んだ半面、政権に抑圧された気候変動関連のパワーも高圧で存在する、という人工的なねじれが生じているのだ。
このような状況では、政策に「反動」(気候変動対策への転換)が起きた場合、抑圧から解放されたパワーが爆発し、整った素地にも乗る形で、気候変動関連の投資、対策の進展が一気に大きく進む可能性が高い。
以上が筆者の考察する「ねじれ構図」についてだが、もうひとつ、この3年半のトランプ政権で発生している重大な特徴がある。ちょうどいま、「反動」という表現を用いたが、そのもうひとつの特徴とは、政府の政策自体が極めて反動的になってきていることである。
継続性なき外交の前例を作ったトランプ大統領
国家の政策、特に外交政策においては継続性というのが暗黙裡で前提とされている。そうでなければ、国際約束(条約)というものは形骸化してしまい、国際法体系も前提が崩壊してしまうからである。
であるにもかかわらず、ビジネスマンであるトランプ大統領は、政策の継続性という観点にためらうことなく様々な「チャレンジ」をした。
オバマ前大統領の否定を軸とした同大統領は、特に気候変動政策については、トランプ色の目玉としてその反動的傾向が非常に強く出た。
パリ協定からの脱退の試みは、国際的なコミットメントである継続性という前提への大いなる「チャレンジ」であった。しかし、この継続性の否定は同時に、民主党政権が政権を握ったときにいつでもそれら(トランプ大統領下の政策)をひっくり返すことを可能にした。
つまり、本来では見られないほどの反動性を米国は帯びた状況になったのである。もちろん、気候変動についてもそうだ。
トランプ大統領が、オバマ前大統領のレガシーであった気候変動対策の推進を否定すればするほど、民主党陣営の掲げる気候変動対策は急進性を増すことになる。バーニー・サンダース陣営との指名選争いをする中で受け入れていったこともあり、現状、バイデン陣営が打ち出している気候変動政策においては、パリ協定への再加入は大前提として、遅くとも2050年に100%クリーンエネルギー、ネットゼロエミッションを達成するという内容を含め各種野心的な目標が掲げられている。
様々な特徴はあるが、例えば将来の貿易合意を締結するには相手国がパリ協定の目標へコミットすることを条件とするという現在のバイデン案は、気候変動対策の推進を、貿易という大きなテーマと直接結びつけ、かつ、条件づけているという点で急進的である。こうしたこれまで見られないような急進性が民主党案の特徴となっている。
さて、やはりこうなると関心は大統領選挙の行方と、その裏にある気候変動関連の思惑である。
トランプ大統領は、大統領になる前の発言をかなり遡れば、オバマ政権に対して気候変動対策を取るよう求めた公開状に名を連ねる等、実は気候変動対策推進派であったこともあり、ほんとうのところでは気候変動に対する信念というものはないことが分かる。
また、その真偽のほどは検証が必要であるとはいえ、今般のボルトン前補佐官による暴露本には、「大統領選挙にいかに勝つかが大統領の関心である」とのニュアンスの言及がある。
これまでの同大統領の行動からすればまさに合点がいくものであり、気候変動に信念がないトランプ大統領は、気候変動を選挙に勝つためのツールとして利用していたと筆者は見ている。
すなわち、同氏が掲げるアメリカ第一主義という大方針と保護主義的カラーに合致するのが化石燃料関連産業の保護、すなわちパリ協定体制の否定なのであり、実際、イリノイ州以外のラストベルト州(インディアナ、ウィスコンシン、オハイオ、ペンシルバニア、ミシガン)での支持を取り付けたことが大統領選挙に勝つ道筋をつけている。
気候変動対策への反対を押し出しつつ、そうした地域の雇用の創出・保護、経済再生を掲げたことで同地域ではトランプ大統領の支持基盤が形成された部分もあり、それ故に自分の再選のための支持基盤を維持するとの観点から、同大統領は一貫してパリ協定体制に反対の立場を貫いてきたのであろう。
先述した2017年のトランプ大統領のパリ協定脱退表明のステートメントで、トランプ大統領が、自身の当選を決定づけたラストベルトの同大統領支持を意識して「I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.(私はピッツバーグの市民を代表するべく当選したのだ。パリ市民のためではない)」と述べたのも、ピッツバーグをはじめとする工業地帯が石炭の使用を前提とする産業に立脚していることを顕著に表したものであり、トランプ色の濃い特徴的な一説である(かつ、パリという単語を出して、しっかり否定するところが同大統領らしい)。

米国の政権交代で起こりうることを見誤ってはいけない
ここまで大事にしてきた支持基盤であるが、皮肉なことに、2020年6月下旬時点の調査においては、Real Clear Politics社、CNBC、Harper社、FOXニュースのいずれにおいても、大統領がここまで特出して取り上げたピッツバーグが所在するペンシルベニア州のトランプ、バイデン両氏の支持率は、バイデン大統領支持が上回っているという結果が出ている。
しかもこれはペンシルベニア州に限った話ではない。ラストベルトのうち、元々民主党支持基盤の強いウィスコンシン、ミシガンの両州だけではなく、近年の傾向ではどちらかといえば共和党色の強いインディアナ州においても現時点(2020年6月)での各種世論調査ではバイデン氏が優勢な状況にある。
もちろん、世論調査の結果が必ずしも大統領選挙につながらないのは前回の選挙が証明しているので、これはあくまで一つの指標でしかない。それでも共和党寄りのFOXニュースの米国全体の世論調査の結果でもバイデン氏が優勢であるとの結果が出ていること、そして、それにトランプ大統領がいら立ちを隠せなかったことは、いかにトランプ大統領が追い込まれつつあるかを顕著に示している。
米国の揺らぎとそれに影響を受けたこういう大統領選挙に向けた動静、それはある種の予見性というものを民間セクターにもたらし、気候変動に関してたまった圧力のピンが外れるウォーミングアップが米国では始まろうとしているのではないか。それが国際的にも当然に影響を及ぼすとして、日本の政府、民間セクターは、果たして適切なタイミングで波に乗っていけるのか。米国の揺らぎの各事象だけを見ていては、事を見誤るのであり、水面下で起きていることに目を配っていくことが大事である。
いずれにせよ、今年11月3日の大統領選挙までは米国の一挙手一投足から目が離せない。どのような些細なことにどのようなサインが隠されているかわからないのであり、そしてそのサインが気候変動の文脈でもたらす国際的なインパクトは、非常に大きいからだ。
引き続き、米国の動向は追っていきたいと思う。次回はなぜ、この米国の動向が国際的な気候変動対策の進展に大きな影響を及ぼすのかについて、よりグローバルな観点から考察していきたい。また、本稿の始めに大統領選挙の翌日がパリ協定脱退の期限である巡り合わせに言及したが、そこにこそ考察すべき論点が隠されていると筆者は考える。この点についても今後触れていきたい。
参照
- パリ協定
- トランプ大統領によるパリ協定脱退表明時のステートメント
- パリ協定脱退手続き時の国務省プレスステートメント
- We Are Still In
- Global Climate Action Summit
- Apple社による再生可能エネルギー調達100%達成プレスリリース(和文)
- Google社による再生可能エネルギー100%達成
- 2018年の米国の温室効果ガス増(米国環境保護庁HP)
- バイデン陣営が公表している気候変動政策
- オバマ政権に対して気候変動対策を取るよう求めた公開状にトランプ氏が署名していたとの報道(TIME誌)
- ボルトン前大統領補佐官の暴露関連報道
- トランプ陣営とバイデン陣営の各種世論調査結果(Real Clear Politics社とりまとめ)
- FOXニュースによる大統領選挙世論調査
- トランプ大統領によるFOXニュース世論調査結果批判報道
