年末に行われたCOP25は、気候変動問題が世界的に注目されるなか行われたが、具体的な成果を見出せないまま終わった。なにがCOPに今、求められ、そしてうまくいかなかったのか。COP25が示した気候変動の国際交渉の困難な状況について、The International Institute for Sustainable Development(IISD)の日報(ENB)、および関係者への取材などをもとに、独自の視点でレポートする。
何の成果もなく、世界の分断が可視化されたCOP25
2019年12月2日から15日にかけて、スペインのマドリッドで、COP25(気候変動枠組み条約第25回締約国会議)が開催された。
期待されたのは、主に3つの論点で合意ないし道筋をつけることだった。具体的に言うと、ひとつは市場メカニズムに関する「パリ協定の第6条」の合意。ふたつ目は気候変動の被害に関する「ワルシャワ国際メカニズム(WIM)」の主に資金の問題。そして3つ目は各国の削減目標(Nationally Determined Contribution:NDC)の引き上げの機運の醸成だ。
しかし、前のふたつについては合意することができず、3つ目の削減目標の野心的な引き上げもなかった。
何の成果もなく、むしろ世界の分断が可視化された、そんなCOPといえそうだ。

会期13日目(延長2日目)のクロージング全体会議
UNclimatechange - https://www.flickr.com/photos/unfccc/49152326513, CC 表示 2.0, リンクによる
裏切られた期待。「野心的な目標」には至らず。
今回のCOPの本質的なテーマは、各国の温室効果ガス排出削減目標の引き上げだった。それは、議題として取り上げられたものというよりも、各国への具体的なコミットメントを求めるものだった。
パリ協定の目標は、地球の平均気温の上昇を2℃未満、できれば1.5℃未満に抑制することだ。各国のCO2などの温室効果ガス(GHG)排出削減目標は、パリ協定の目標に合致したものが求められる。
ところが、各国が自主的に設定した2025年、ないし2030年のGHG排出削減目標は、2℃未満に抑制するのに必要な削減量の半分程度にとどまる。したがって、削減目標のさらなる「野心的」な引き上げが必要となっているのだ。
2018年10月に公表されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の「1.5℃特別報告書」*1では、気温上昇2℃の場合と1.5℃の場合では気候変動の影響について、圧倒的な差があることが示された。そして、1.5℃未満に抑制するためには、2050年にはGHG排出ゼロを目指す必要があるということだ。
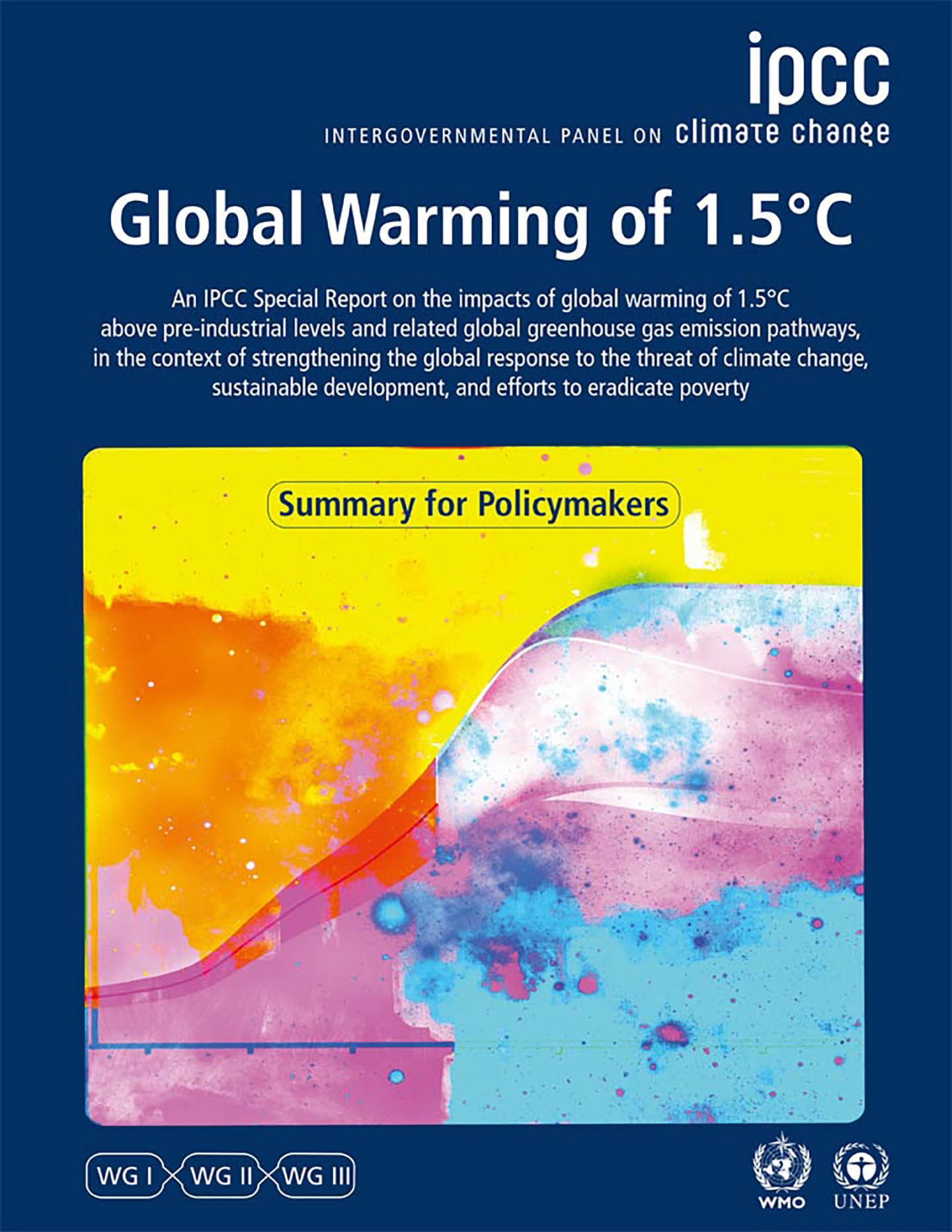
IPCC 1.5℃特別報告書
2020年には削減目標の再提出が各国に求められる。このときに、引き上げが行われるような方向付けができるかどうかが、COP25のポイントだった。
再提出前であるCOP25の段階で各国に求められたのは何か。それは、実際の削減目標にこだわらず、具体的な削減方法についてのコミットメントだった。例えば、炭素税などの国内制度の整備、あるいは石炭をはじめとする化石燃料関連の投資の抑制や石炭火力発電所の廃止などについて、それぞれの国が事情に応じて表明してくれればいい、ということだった。長期的な削減目標への言及や、後述する第6条問題、WIM問題への合意、2019年に公表されたIPCCの新たな2つの報告書の取り扱いも、このコミットメントに含まれるはずだった。
結果からいえば、期待は裏切られた。
削減目標の引き上げを表明した国は84ヶ国にのぼった。また、2050年GHGネットゼロを表明したのは73ヶ国。ただし、その多くは小規模な途上国であり、OECD加盟国はEUを除くとわずか5ヶ国だ(ノルウェー、チリ、アイスランド、メキシコ、スイス。この他、カナダとニュージーランドはNDC引き上げは表明していないが、2050年GHGネットゼロを表明)。
さらに、2019年に新たに公表された、IPCCの2つの特別報告書が、気候変動問題の深刻な状況を報告しているにもかかわらず、その報告書そのものが十分に顧みられることもなかった。
ブルーCOP(憂鬱なCOP)
IPCCが新たに公表した2つの報告書とは、「気候変動と土地に関する特別報告書」*2および「海洋・雪氷圏に関する特別報告書」*3だ。
前者は、農林業によるGHG排出量が全世界の23%に及ぶことを示し、農業からの排出削減と林業による吸収増が必要であることを示したものだ。イメージとしては、牧草地に植林して、畜産業からのメタンを削減し、CO2を吸収する、といったところだ。気候サミットで小泉環境大臣がステーキを食べたことを批難されたのも、こうした背景からだ。
一方、「海洋・雪氷圏に関する特別報告書」は、より深刻な内容となっている。海面上昇だけではなく、海洋の酸性化と溶存酸素の減少による水産資源の減少などが示されている。高山地域や低地、北極圏、島しょに住む人々が氷河の融解や海面上昇に影響を受けるのはもちろんのこと、気象や食料など、様々なマイナスの影響が大きく、プラスの影響は少ない。そのため、野心的な行動が緊急性を持って求められるという。まずは、海洋について、継続的な観測が必要ということだ。
特に、今回は海洋におけるGHGによる深刻な影響が明らかになってきたことから、2009年のCOP15以来、海洋の問題を気候変動に位置付けるための「ブルーCOP」だとされ、12月7日は海洋行動デーとなった。
2つの報告書が示していることを、わかりやすいイメージとするなら、「将来は肉(特に牛肉)を食べるのは贅沢であり、魚はもはや食べられなくなる」というものだ。
しかし、こうした地球の危機的状況を示した報告書に対し、一部の国は「留意する」程度にとどめようとした。最後まで、科学が示した危機と政治との間に、大きなギャップが残ったままだった。
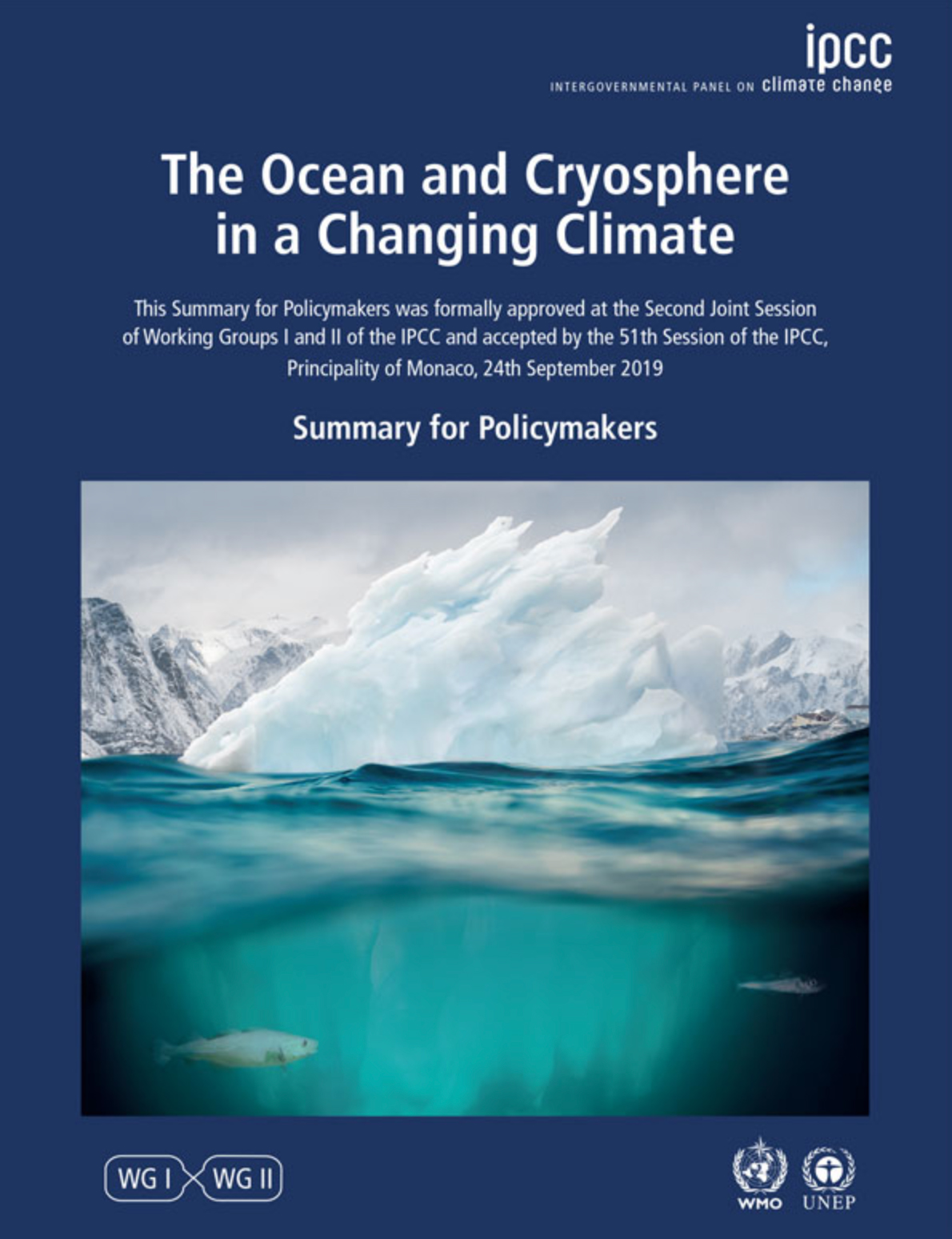
IPCC海洋・雪氷圏特別報告書
*2:IPCC 土地関係特別報告書:環境省https://www.env.go.jp/press/107068.html
*3:IPCC海洋・雪氷圏特別報告書:環境省 https://www.env.go.jp/press/107242.html
ハイライトとなった2019年12月11日。
COP25のメッセージ的なハイライトは、12月11日に行われた一連のハイレベル・イベントだった。ここでは、さまざまな立場から、気候変動問題が非常事態であるということが強調された。第1週に、マドリッド市街では50万人がデモを行い、気候変動の交渉から対策の実施へシフトすることを求めたが、その熱がこの日につながっているともいえるだろう。
例えば、スペインのテレサ・リベラ環境保護大臣は、「(パリ協定で)同意したことと行っていることのギャップが拡大」していることを指摘、「(排出削減に資する)より多くの行動を恐れる者の名前を公表し恥じ入りさせるよう」に呼びかけたという。
また、ポツダム研究所のヨハン・ロックストローム氏は気候変動の科学が過小評価されていることを指摘、「2℃が地球の限界だ」と強調した。
グリーンピース・インターナショナルのジェニファー・モーガン氏は、1.5℃以下に抑制するための緊急措置を政治指導者に対して促した。
さらに、ヤング・アクティビストのグレタ・トゥーンベリ氏は、公平性を強調し、「世界の人口の10%が排出量の半分を出している」ことを強く指摘した。
この他にも、スペインの大臣と国際宇宙ステーションの司令官、国連事務総長の対話をはじめ、途上国支援やGHG排出削減などに関する閣僚級の議論といったイベントが行われた。
さまざまなアクターが、気候変動問題の危機的状況を訴えたこの日は、COP25が世界から何を求められているのかを明らかにした日でもあっただろう。

12月11日、COP25の会場で。右:スペインのテレサ・リベラ環境保護大臣、左:グレタ・トゥーンベリ氏 スペイン気候保護省のFlickrより
Ministerio para la Transición Ecológica - https://www.flickr.com/photos/mitecogob/49202652893/, CC 表示 2.0, リンクによる
パリ協定6条は機能しないまま
パリ協定のルールブックのほとんどは、2018年のCOP24で合意されたが、その中にあって第6条は合意されず、今回のCOPまで先送りされた、ほぼ唯一の条文だった。
第6条の内容は、いわば国どうしのGHG排出量クレジットの取引に関するもので、市場、もしくは非市場の取り組み、メカニズムに関するもの。いわゆる京都議定書における京都メカニズムの後継となるものだと考えてもらえばいい。
問題となる項目は3つだ。
第6条第2項、協力的アプローチの条項。これは、日本政府が提唱する二国間クレジット(JCM)を含むもので、ある国が他の国でGHG排出削減を行ったときに、排出量クレジットを移転するというものだ。
第6条第4項は、京都メカニズムのCDM(クリーン開発メカニズム)に相当するもので、国連管理型メカニズムをどのようにするかの条項。第三者機関の運営組織がクレジット認証などの手続きを行う点が、第2項と異なっている。手数料がかかるが、その収入が途上国支援にあてられる。
そして第6条第8項は、非市場アプローチとなっている。具体的に、どのような事業なのかは明確ではないが、非市場アプローチで途上国の支援を行っていく、ということだろう。ODAのような形で先進国が途上国のGHG排出削減を支援するようなイメージなのかもしれない。
しかし、第6条については、会期を44時間も延長したにもかかわらず、合意に至らなかった。何が問題だったのか。
第2項では、第4項と同様に収益の数%を途上国支援に使うという点について、先進国が反対したことが大きい。また、削減目標は国によって定義の仕方が異なっている。複数年度の削減目標を持つ国と単年度目標の国との間で、どのようにGHG排出削減量を移転するのか、という点も争点となった。
第4項では、主にブラジルがダブルカウント防止のための調整に反対した。これは、他の国がホスト国でGHG排出削減を行ったとしても、その分ホスト国の削減目標を厳密に調整しなくてもいい、ということだ。また、京都メカニズムのCDMによるクレジットのパリ協定への移転が可能かどうかという点も、合意できない争点として残った。
また、第2項と第4項に共通する争点として、人権に関する条項の追加、クレジット価格の流動性リスクなどに対するセーフガードなども含まれていた。
第6条について合意できなかった影響としては、2020年からのパリ協定の運用に障害が生じること、とりわけGHG排出削減の透明性に関わる点が懸念される。また、それ以上に、各国が削減目標の引き上げに積極的になる機運につながらないことが問題だ。
他方、パリ協定の削減目標は京都議定書と異なり、自主的な目標設定となっているため、排出量取引のようなメカニズムの必要性はそもそも少なくなっているのではないか、という指摘もある。その意味では、第6条は重要ではない、という指摘もある。
日本においては、二国間クレジットのしくみを、将来の合意を前提として進めていくことになるだろう。

パリ協定採択時のCOP 21(2015年)に参加した各国代表。
Presidencia de la República Mexicana - https://www.flickr.com/photos/presidenciamx/23430273715/, CC 表示 2.0, リンクによる
ワルシャワ国際メカニズム(WIM)も合意に至らず
COP25のもう一つの重要な議題であるWIMもまた、合意に至らなかった。WIMは、気候変動問題による被害や損失に対応するために設置された組織だ。しかし、資金不足から、十分に機能していないのが現状だ。
今回はWIMのレビューと資金がテーマとなった。WIMは、文脈としては、先進国による気候変動がもたらした被害や損失に対応するためのものということになる。したがって、資金は先進国が負担すべきだ、というのが途上国の主張だ。
これに対し、とりわけ米国は先進国の責任を回避する方向で交渉し、先進国全体としても資金の拠出に合意しなかった。また、レビューそのものも、何を対象にするのかという合意ができなかった。そこには、WIMが、巨大台風や干ばつ、海面上昇の被害を明らかにしていくほど、補償が拡大していくという懸念がある。
一方、WIMとは別に、先進国が2020年まで、気候変動対策として国連に毎年拠出する1,000億ドルの長期資金についても議論されたが、実際に拠出されるのかどうか、進捗を引き続き評価していくということのみにとどまった。さらに2020年以降の長期資金についても、合意はできていない。
地域間、世代間、強者と弱者の間に求められる「共通だが差異ある責任」とは。
COP25の結果を考えたとき、先進国と途上国の対立という構図は、何も変わっていないことがわかる。気候変動問題が深刻な問題であることは理解していても、先進国の政府は排出削減や資金拠出に十分な対応をせず、途上国の政府は自国での対応より先進国の対応を求める、ということだ。
京都議定書では1992年の気候変動枠組み条約から続く「共通だが差異ある責任(Common but Differentiated Responsibilities)」という明示的な合意があったが、パリ協定においてはこの合意はない。先進国が「差異」に対応しなくなったということでもある。しかし、WIMが示すように、気候変動問題は、例えば将来は膨大な難民を生み出す可能性がある。いずれ先進国はこれを引き受けることになる。その意味では、気候変動問題は今もなお、南北問題でもある。
また近年のCOPにおいては、グレタ・トゥーンベリ氏に代表される、若い世代の活動が目立つようになってきた。これは、若い世代が、世代間の不公平を訴えているものだ。先行する世代と比較して、若い世代は気候変動問題により直面する生活を送る可能性が高い。その意味ではトゥーンベリ氏が演説で示した怒りは当然だといえるだろう。世代間においても「共通だが差異ある責任」が問われている。
今回のCOPでは、これまで以上に人権やジェンダーについての議論が大きく取り上げられた。あたりまえだが、気候変動の影響は、女性、子供、障害者等、脆弱な立場にある人にも及ぶ。そうした中にあって、とりわけジェンダー平等と女性のエンパワーメントが、公平性を持った気候変動対策に不可欠ということだ。例えば、気候変動対策に伴う労働力の移行にあたっても、ジェンダー平等の強化が必要だ。さらに、条約事務局においても、ジェンダーバランスが求められる。条約事務局長は直近の2代は続けて女性が就任していることも、このことと無関係ではないだろう。ジェンダーギャップが121位の国である日本では、なかなかピンとこないことかもしれないが。

12日目の全体会議場
UNclimatechange - https://www.flickr.com/photos/unfccc/49209435976/, CC 表示 2.0, リンクによる
諦めてはならない。COP26は11月開催
気候変動問題の責任を引き受けられない各国政府に対し、自治体や民間企業、NPOなどの非国家アクターは、意欲的なGHG排出削減に取り組み、あるいは情報発信を行っている。
もはや、気候変動対策は、政府ではなく非国家アクターが主導しているのではないかという見方すらできる。この非国家アクターの中心となるプレーヤーとしては、金融セクターの存在感が大きい。見方を変えると、世界を変えるのは政治ではなく経済なのではないか、とすら思えてくる。気候変動対策の経済合理性を誰がもっともよく知っているのか、ということなのだが。
COP26は、2020年11月9日-19日にかけて、英国のグラスゴーで開催される。そこでは引き続き、第6条や資金の問題が議論される。同時に削減目標の野心的な引き上げが今回以上に注目されることだろう。
パリ協定:国連https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
パリ協定:外務省https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page24_000810.html
(取材・執筆:EnergyShift編集部 本橋恵一)

