
建設アスベスト(石綿)最高裁判決から考える 気候変動の被害の回避
2021年5月17日、建設現場でアスベスト(石綿)を吸って被害を受けた作業員や遺族らが国と建材メーカーに賠償を求めた訴訟で、最高裁が原告の主張をほぼ認める判決を言い渡した。訴訟が長期にわたっただけではなく、そもそもアスベストの有害性に対する国の対応が不十分だった。この問題を気候変動に置き換えたとき、同じ構造の問題を抱えていることがわかる、弁護士でもある気候ネットワーク理事長の浅岡美恵氏はそのように指摘する。
アスベスト被害に最高裁判決
アスベスト(石綿)は「静かな時限爆弾」といわれてきた。2021年5月17日に言い渡された最高裁判決は、判決前から注目されてきた。大きく報道されたところだが、13年に及ぶ訴訟で何が争われ、どう判断されたのかを解説し、気候変動被害の回避の視点から考える。
今回の判決は、神奈川、東京、大阪、京都の4つの集団訴訟での高裁判決についての上告にそれぞれ応答したものだが、中心は神奈川訴訟である。これまでに国とアスベスト含有建材メーカーの責任は基本的には確認されていた(国やメーカーの上告は不受理)が、責任の範囲やどのメーカーの建材にばく露して罹患したものか特定できない場合のメーカーの責任など、いくつか論点が残されていた。
アスベストは石綿という名のとおり、その紡織性、拡張力、耐熱性などから、木造・鉄骨造の建築現場で内装・外装工事や工場等の配管の保温材など様々な用途に利用されてきた。そしてその被害は、アスベスト紡職工場や建設現場でのばく露だけではなく、工場周辺の住民にも及んだ。体内に吸い込まれたアスベストは肺に到達し、特有の中皮腫や肺がんなどを発症するまでに、数十年ともいわれる長い潜伏期間がある。ばく露量にしきい値(最小値)はないとされている。
日本は輸入国で、高度成長期に急増し、1974年のピーク時には35万トン、1988年の32万トンを境に減少に転じたが、2005年まで輸入、消費が続いた(最高裁判決)。米国のピーク(1973年)が80万トンというから、これと比較しても日本は相当の量を消費してきたことになる。
輸入したアスベストの約7割が建設現場で使われたという。労働者の1割が建設業に従事していた時代に大量に使われたことから、潜在的な被害者の多さは容易に想像がつく。一昨年においても約1,000人もが新たに労災認定されているという。
今回の判決は、国の対応が不十分で違法とされた期間を、これまでの1981年~1995年(東京高裁)から1975年~2004年に広げた。国と建材メーカーの一人親方と呼ばれる作業者に対する国の責任も認められた。
メーカーの異なる3種類の建材を使って罹患した作業者について、個別にどの程度罹患に影響を与えたのかは明らかでないが、シェア率による割合を寄与度としその割合で損害賠償義務を認めるとした。
これは、民法の共同不法行為の規定を被害者保護の見地から類推適用したもので、「被災大工らは、建設現場において、複数の建材メーカーが製造販売した石綿含有建材を取り扱うなどにより、累積的に石綿粉じんにばく露しているが、このことは、これらの建材メーカーにとって想定し得たこと」と述べている。残念ながら大阪高裁判決で認められていた屋外での作業については認められなかったが、他の論点では被害者救済の方向に統一された。
個別メーカーの製品による粉じんのばく露量が被害者に罹患をもたらしたばく露量全体の一部にとどまる場合に市場でのシェアによる寄与度の範囲で責任を負うとの考え方は、気候変動における大排出企業の責任にも通じる。実際、今、ペルーの農夫が原告となっておこしたドイツの裁判所での訴訟では、ドイツの大電力会社に対し、その累積排出量の割合の負担を求めて闘っている。
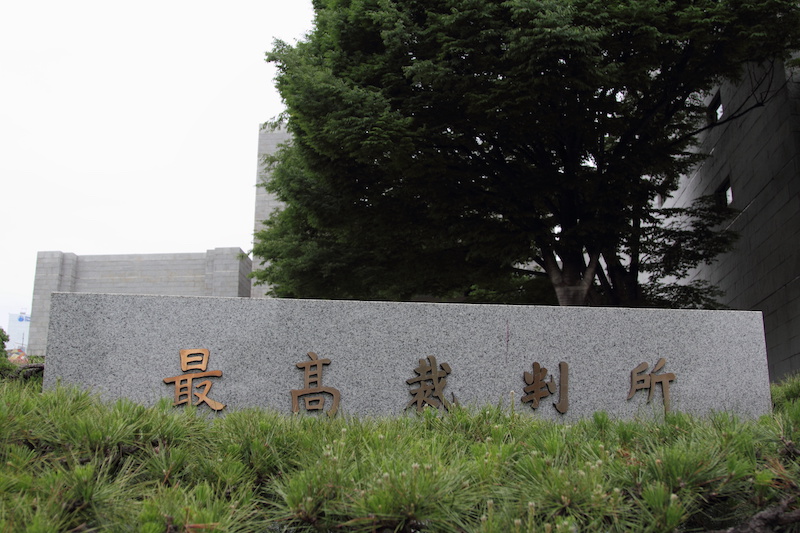
国の違法は1975年から
工場労働者の訴訟は既に最高裁で確定している。今回の原告らは建設作業でアスベストにばく露して石綿肺や肺がん、中皮腫に罹患した人たちやその遺族である。
国に対する請求の根拠は国家賠償法という法律である。メーカー責任は民法の不法行為責任の規定による。どちらもアスベスト粉じんにばく露することによる生命、健康被害を予見できたことが前提となるが、国の責任が認められるためには、国の規制権限(この場合は労働安全衛生法による)の不行使が「その権限を定めた法令の趣旨、目的やその権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」という要件が加えられる。通常、このハードルはとても高い。
一方で、対象となる労働安全衛生法の趣旨、目的は、「労働者の労働環境を整備し、その生命、身体に対する危害を防止し、その健康を確保することをその主要な目的とし、できる限り速やかに、技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、適時にかつ適切に行使されるべき」ともしてきた(平成16年、平成26年最高裁判決)。生命健康被害の防止のための「適時適切の原則」として知られる。
今回の最高裁では、内外の医学的知見に基づき、石綿粉じんのばく露と肺がんや中皮腫への罹患の関連性や遅発性は1972年には明らかになっており、国も1973年に海外の状況にあわせて粉じん濃度規制を強化し、75年に警告表示の掲示が義務付けられたこと等をあげ、労働大臣は1975年にはアスベストの危険性を具体的に記載して掲示し、防じんマスクを使用させることを義務付けるべきであったと結論づけ、1975年から2004年までの間、違法であったとした。
通達による表示の内容とは、「多量に粉じんを吸引すると健康を損なうおそれがあります・・」「取扱い中は、必要に応じ、防じんマスクを着用ください」というもので、「健康のために吸い過ぎに注意しましょう」との、かつてのタバコの表示を思い出させる。
警告とは、どうしなければいけないか、何をしてはいけないか、その場合に何が起こるかを具体的に表示していなければならない。これでは警告とはいえないとして違法とされた。警告の掲示を義務付けた趣旨は、雇用関係のない者を保護の対象外としているとは解しがたいとし、建築現場で働く、雇用関係のない一人親方の救済にも繋がった。
国との訴訟の長期化
それにしても、提訴からの13年は余りに長い。健常な人間でも紛争を抱えた生活は耐え難いものだ。アスベスト中皮腫等の特徴として、長い潜伏期間を経て、ひとたび発病するや、その進行はとても早いということがある。今回の判決の原告を含め、全国各地の原告約1,200人のうち、これまでに亡くなった方が700人に及ぶと聞き、絶句する。せめてもの司法による事後救済がこれでいいのかと、判決のたびに思う。
しかも、まだ終わりではない。最高裁は論点についての考え方は示したが、東京高裁に審理を差し戻した。国との間では、未提訴者を含めた和解による救済の道筋が見えてきたが、建材メーカーとの間はこれからである。
裁判が長期化する理由に、被告らが請求額を超える訴訟費用をかけても徹底的に争うということがある。日本のように訴訟になる事件が少なく、クラスアクションのような制度もない国では、訴訟を維持し、勝訴に至ることがどれほど骨の折れることかを原告に対して知らしめる効果が大きいからだ。
この態度は、国の場合により鮮明となる。国の代理人の多くは裁判官出身の訟務検事であり、短期間で交替するため疲れを知らない。訴訟費用の心配もない。国は不死身なのである。しかも、客観的な事実であっても、ともかくすべてを否認し、また争う。かくして、あれもこれも原告側の立証対象となり、証拠書類が山のように積み上がる。
少なくとも欧州の気候変動訴訟ではそうではない。オランダのNGOがオランダ政府の2020年削減目標について1990年比20%削減は不十分で25%とするよう命じた事案の最高裁判決(2019年12月20日)には、気候科学が示す気候変動による危険とその結果に関する事実は、当事者間、即ち原告らと被告国との間で争いはなかったとある。
だが、現在の日本における、横須賀などでの石炭火力発電所建設に係る環境アセスメント手続きの違法性が焦点の事件でも、地球温暖化による気候変動の影響についても、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)のレポートの存在や気象庁の報告書の存在だけを認め、その内容については不知とか否認と答弁する。
石炭火力発電からの二酸化炭素は天然ガスの約2倍との経済産業省の資料にも記載されている事実についても、国の態度は否認である。その挙句、国の広範な裁量権を主張する。しかも、最高裁は国の行為に理解があるものと確信しているらしい。

46年後の違法宣告
遅ればせながらではあるが、判決で国や企業の対応に法的にけじめがつけられることはいいことだ。だが、国の規制権限を適示適切に行使しなかったと何十年も経って批判されるようなことがまかり通ってきた背景に、日本では業界の自主的取組に任せるなど、行政の業界擁護の姿勢がある。
裁判所は、生命、健康にかかるケースでの賠償責任は、国や企業に厳しい判断をしてきたが、事前差し止めには消極的で、行政の裁量を広く認める。被害を防止する措置をとらなかったことが違法とされるのが46年も経ってからなのでは、あまりに犠牲が大き過ぎる。
これを気候変動の場合で考えてみよう。パリ協定で2℃(1.5℃)の実現が国際社会の目標となり、国連グテーレス事務総長は2020年以降の石炭火力発電所の新設を中止するよう求めている。
そんな今、石炭火力発電所を新設し、40年間、稼働率70~80%で稼働させようとするのはパリ協定の目標と相容れない。だが、日本では、環境アセスを経て、今も6ヶ所で建設中(約500万kW)であり、他にもつい先ごろ稼働を始めた発電所もある。これらの発電所の建設稼動を許してきた手続きが何十年後に違法だったと宣告されてもどうしようもない。グレタ・トゥーンベリさんら若者が大人たちに突き付けているのはそのことだ。
2021年3月24日、ドイツの憲法裁判所は、議会に対して今年末までに気候変動法を改正することを命じた。気候変動被害は人権を脅かすもので、カーボンニュートラルに至る科学的に一貫した削減目標が法定されていないのは、彼ら若者たちの市民的自由を侵害するものというのがその理由である。ドイツ政府の対応も早かった。5月6日にカーボンニュートラルを2045年に前倒しし、2030年と40年目標も引き上げる改正法案を閣議決定した。
気候変動の被害は回避するしかない。裁判所には今、世界でそのための役割が期待されている。
気候変動の最新記事